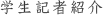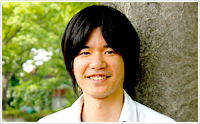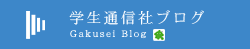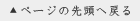京都大学経済学部3年生の高橋佑吉さん(21)はギフト販売や料亭の運営など米にかかわる様々な事業を展開する「株式会社八代目儀兵衛」(京都市下京区)で今年の2月から11月までインターンシップを行った。データ処理から皿洗いまで多岐にわたる仕事を経験。高橋さんは、この期間を「修業だった」と振り返る。
「やってみたいと思ったことはすぐ実践する」と話す高橋さん。インターンに対して、社会人と一緒に働けることに「かっこいい」という印象を持ち、半年間行える長期インターンの存在を知った2年生の初めころから挑戦したいと考えていた。インターンの合同説明会では、参加していた10社の中から同社を選んだ。理由は同社の橋本隆志社長(40)があえて「うちは相当厳しい」と説明し、その言葉に「他とはオーラが違う」と感じて興味を持った。
しかし、開始しばらく高橋さんは理想とのギャップに苦悩。社員と肩を並べて堂々と仕事をする自分のイメージを持っていたが、データ処理などのデスクワークや社内イベントの企画などが上手くできない。叱られる事もあり「こんなこともできないのか」と悩む日々だった。そんな3月中ごろ、社員に呼び出され「料亭の洗い場で仕事をしては?」と勧められた。思わぬ仕事に「マジで!?」と当初は戸惑いがあったが、現場をより知る事ができると聞き、挑むことに決めた。
仕事は皿洗いのほか、味噌汁の準備や注文の配膳など。耳のインカムと周りから、絶え間なく指示が送られ、お昼のピークからの3時間は休む間もなかったという。インターン期間の1カ月、辛さに耐えながら「このまま終わりたくない」と学べる点を模索。すると、料理を用意する中で「お刺身の注文が多ければ比較的年配の方が多い」「肉系統の注文は若い人が多い」と、注文の傾向や客の年齢層など、たくさんの気づきがあった。皿洗いというひとつのことからでも多くを学べる事がわかった。
洗い場での気づきをきっかけに、社内イベントの企画や料亭の改装の手伝いなどの仕事をこなしていった。7月には料亭で働く社員に、取り扱う米の精米過程を実際に見てもらおうと、同社の米を作っている与謝野町(京都府)の観光を企画。稲を作っている田んぼや農家を案内し、イベントを成功させた。高橋さんは「この企画では今までインターンで学んだことを活かせた」と話す。
普段の仕事では忘れられない思い出があった。めったに他人を褒めない社員が食事中、「最近ようがんばっているな」と、つぶやいたときは嬉しくてたまらなかった。
高橋さんはインターンについて「非常に辛く、まさに修業だった。でもやってよかった。根性がついた」と思い返す。最近では家族や友人から「自信がついたな」「目つきが違う」と言われるようになった。また、この経験から経営者になるという夢も生まれた。「社員やお客様など人を大事にし、未来志向の会社を作りたい」と話す。
橋本隆志社長はインターン生に対し、その場で成果を出してほしい訳はない。この経験で得たものは実際に社会に出てから活きてくると考えているからだ。そして「インターンのメリットを学生に与えるために、身を削っていく。そして将来、形はどうあれ一緒に仕事ができる関係を期待している」と話した。
(取材後記)
インターンをしたいと思ったことがない。どうしても、「ただ働き」「仕事がつらい」という印象がある。少し前まではインターンを好んでやる人の気持ちが理解できなかった。しかし、何人かのインターン生を取材して、自分なりのインターンの利点を発見できた気がする。それは、「怒ってくれる人の存在」だ。
大学生にもなり、さらに一人暮らしを始めてしまうと、怒られる事がほとんど無くなった。自分を見てくれる大人が高校時代から一気にいなくなる。怒られる事がなくなると、大人になった気になって調子に乗ってしまうことや、逆にどこまでがいけない事なのか分からず消極的になる。インターン生は皆、周りによく叱られたと話すがそれこそが社会に出るとあまり無い経験なのかもしれない。特に中小企業の場合は、本格的な仕事も体験させるなど、会社が大企業よりも大きなリスクを背負いながら学生に成長の場を与えているように思える。そのため学生のためを思って叱っているのが強く伝わる。
- 【中小企業で働く学生を追う】京都大学 高橋佑吉さん(2012.12.17)
- 「仁張工作所」の仁張正之社長に聞く(2012.11.27)
- 「グラント」 山崎元彰社長に聞く(2012.10.09)
- 【中小企業で働く学生を追う】京都大学大学院 杉本悠さん(2012.09.21)
- 学生が中小企業に恩返し 企業の魅力を伝える「夢造」(2012.09.10)
- 田代珈琲・田代和弘社長に聞く(2012.08.07)
- 顧客イメージを家具に(2012.07.11)
- 元ボクサーらが大阪で歴史塾開講(2012.06.20)